
投資で節税♪新年度に始めたいNISA、積立NISA、IDECOとは? ~ その1では、NISAと積立NISAの違いやメリット・デメリットについて解説しました。
ここでは、iDeCoについて解説しながら、NISA、積立NISA、iDeCoをどのように使い分けるべきか、併用する時のコツについて説明します。
目次
老後資金の形成向けのiDeCo(イデコ)そのからくりとメリットは?
iDeCo(イデコ)とは?

iDeCo(イデコ)は「個人型確定拠出年金」と呼ばれ、自営業者・サラリーマン・公務員・主婦などが任意で加入することが出来る個人で積み立てる年金制度です。
2017年に法改正があり、加入対象者が増えたことで認知度もあがりました。公式サイトでは下記のように説明されています。
加入者が月々の掛金を拠出(積立)し、予め用意された金融商品で、運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取ります。※60歳になるまで、引き出すことはできません。
引用元:iDeCoナビ
http://www.dcnenkin.jp/about/
国民年金や厚生年金とは異なり、個人の意思で加入する・しないを判断することができます。
現在の年金制度では老後の生活保障が万全というわけではありません。
かつ、将来的には減額されるリスクもあります。よって、iDeCoを使って自分自身でも老後に備えてほしいというのが国からのメッセージです。
上限は?
iDeCoは対象によって掛けることができる上限が決まっています。
一般的なサラリーマンの場合、上限で毎月2万3千円まで掛けることが可能です。
iDeCoのメリット・デメリット
iDeCoのメリット ~ 3つのお得

iDeCoの一番のメリットは、やはり税制上のメリットです。税制上3つのポイントで課税がかからなくなるため、資金運用先として注目されています。
所得控除で得する
1つ目のポイントは毎月の掛け金を出す際の免税です。
iDeCoに掛け金を拠出する場合、その掛け金(保険料)は全額が所得控除の対象になります。これはかなり大きな優遇になります。
生命保険で最大1つにつき4万円までしか控除の対象にならない点を考えても、相当大きい優遇であることがわかるともいます。
年収によって戻ってくる金額は異なりますが、4万円~10万円程度還付されるのです。
年収が高ければ高いほど、還付額も大きくなるため有利に働きます。
しかもサラリーマンの場合、年末調整で還付されるので手続きの面でも簡便です。このように非常に優遇されている制度であると言えます。
運用時も非課税でお得
また、運用時にも税金のメリットを受けることができます。通常、分配金や配当・定期預金の金利などの運用益には20%程度の税金がかかってきます。
しかしiDeCoを利用した場合、この20%の運用益はすべて非課税となり、再投資に回ることになります。複利効果を最大限利用できることを考えるとこれも大きなメリットになります。
NISAの非課税が5年間であるのに対し、60歳まで非課税が続くというのは資産形成上大きなプラス要因になります。
受け取る時もお得
年金として受け取る時も控除を受けることが可能です。iDeCoは60歳時点で、一時金または年金として受け取ることができます。
30歳でスタートした場合、30年分の控除枠がつきますので800万円+700万円=1,500万円分が非課税となります。
年間の掛け金が最大25万円程度であることを考えれば、かなりの金額が控除されます。
本来であれば、1,500万円に対して譲渡所得として20%がかかり、300万円が課税されるところが0になるのは、数字の面から見てもお得さが際立っていると思います。
年金として受け取る場合であっても、公的年金等控除が利用可能なため課税金額は少なくなります。
さらに、確定拠出年金は換価不要な資産として確定拠出年金法によって保護されています。よって、仮に自己破産をしたとしてもその財産は清算されず60歳以降に受け取ることができるのです。
セーフティネットとして
個人事業主や中小企業経営の場合、ある程度リスクをとって事業を運営している人も多いと思います。仮に失敗して破産してもiDeCoの掛け金が守られるのは、セーフティネットとしては嬉しいですね。
iDeCoのデメリット
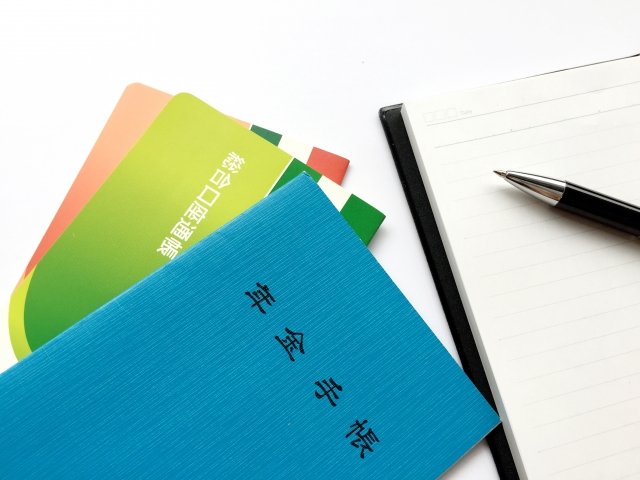
一見万能に思われるiDeCoですが、デメリットや問題点がないわけではありません。
60歳になるまで動かせない
1番のデメリットは、流動性がないことです。
iDeCoは長期投資を前提にしているため、資産を流動的に扱うことができません。あくまで年金という扱いになりますので、60歳になるまでは解約して資金を受け取ることができないのです。
しかし、掛け金の変更は可能ですので仮に生活が苦しくなった場合は掛け金の額を減らすなど、柔軟な対応は可能です。
もともと老後資金の運用としての制度ですので大きな問題になることはないでしょうが、余剰資金の範囲内でやるのがよいでしょう。
投資信託の場合手数料がかかる
また、iDeCoは投資先は主に定期預金・投資信託になります。投資信託は間接的に信託報酬がかかってしまい、かつ売買手数料がかかることもあります。
そんなに大きな金額ではないですが、塵も積もれば山となります。
実際に個別株を運用するのに比べて手軽に始めることができる反面、個別株に比べれば割高になってしまうというのは理解しておく必要があるようです。
iDeCoとNISA、積立NISAは併用すべき?

iDeCoはNISAや積立NISAともに、併用が可能な商品になります。NISAと積立NISAは併用ができない点を考えると、これも大きなメリットだと思います。
iDeCoは先ほどもいったように、長期投資に適した制度になります。
かつ、拠出・運用・受け取りのそれぞれのタイミングで減税になりますので非常に優れた制度です。
また、NISA・積立NISAもそれぞれで税優遇があるため、併用できる余剰資金がある人はぜひ併用するとよいでしょう。
iDeCoとNISAの併用は、意外と難しい?
iDeCoとNISAの併用をする場合、どのように考えればよいでしょうか。
iDeCoは長期投資に向いており、かつNISAは比較的短期や中期の投資に適した制度です。
よって、iDeCoで積み立てに適した商品を選択しながらNISAでは短期的に値上がりしそうな商品を買う、という形で使い分けが可能です。
注意点1
しかしiDeCoとNISAの併用の場合、注意が必要です。一般的に短期的に値上がりしそうな商品は値下がりのリスクもある商品になります。
短期的に値下がりした場合、NISAのメリットを利用することもできず、また損益通算もできないため通常の投資より損をする可能性があることは注意したほうがよいでしょう。
注意点2
さらにNISAの非課税枠は120万円で、iDeCoはサラリーマンの場合は約25万円が非課税枠になります。合計すると145万円の非課税枠があります。
145万円はサラリーマンにとってはけっして小さい金額ではありません。また、枠に無理やり入れようとして普段の生活資金がなくなってしまったら本末転倒です。
自分の投資資金がいくらあるかをしっかり計算しながら、運用することが重要です。
相性バッチリ?iDeCoと積立NISAの関係
一方、iDeCoと積立NISAについては関係が変わってきます。積立NISAとiDeCoは、一緒に使うことでiDeCoのデメリットを補完してくれる可能性があるのです。
途中引出しの可否
- iDeCo:60歳まで掛け金を引き出せない
- 積立NISA:いつでも解約できる
iDeCoの最大のデメリットは、60歳になるまで掛金を引き出すことができないことです。
人生は、何が起こるかわかりません。元気で仕事が続けられれば問題ないのですが、もし何かのきっかけで働くことが出来なくなった場合は貯蓄に頼る形になります。しかし、iDeCoはもちろん引き出すことができません。
しかし、積立NISAの場合はいつでも解約可能です。上記のような不測の事態が発生した場合でも、解約することで生活資金にまわすことが可能です。
iDeCoを老後資金の準備として運用し、積立NISAは、手元資金を増やすための制度と考えることもできるのです。
iDeCoは定期預金もOK
また、積立NISAがインデックス投信がメインの商品になるのに対し、iDeCoは定期預金でも利用可能です。
投資信託はもちろん値下がりするリスクがあります。一方定期預金は値下がりしません。
投資信託が値下がりしたとしても定期預金がクッションになるので、価格下落リスクに柔軟に対応することができます。
また、積立NISAとiDeCoの場合は両方足しても年間の非課税枠は65万円程度です。
この金額であれば無理なく全額使い切ることも可能ではないでしょうか。トータルの非課税枠が大きいのも嬉しいところですね。
まとめ
iDeCoは拠出時・運用時・受取時、それぞれのタイミングで節税ができる非常にお得な制度です。60歳まで受け取れないというデメリットを踏まえても、ぜひ活用すべき制度であるといえるでしょう。
iDeCoとNISA・積立NISAはそれぞれ併用可能です。NISAと併用するよりも積立NISAと併用するほうが、サラリーマンであれば無理なく節税が可能になるかもしれません。
何度もくり返しますが、NISAやiDeCoを活用して国は投資を促進しようとしています。あなたの銀行に眠っている預金もこの機会に投資資金に変えてみてはいかがでしょうか。
iDeCoやNISAで投資信託の商品を選ぶ時に役立つ投資信託の基礎知識やメリット・デメリットについて知りたい方はこちらのページをご覧ください。
投資信託とETFを徹底比較!分配金や信託報酬、メリットやデメリットを解説
