マイホームを購入する時に欠かせない「土地」の権利には自分が所有者となる「所有権」のほかに、所有権を持たないけれど土地を利用できる「借地権」があります。
マイホームの購入で物件探しをしている際に「安い!」と気になる物件が借地権付きの建物であるということもあります。土地の「借地権」については曖昧で詳細が分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、借地権付きのマイホーム購入の時に知っておきたいポイントについて、お話していきたいと思います。

目次
借地権とは?
借りた土地を利用する権利のことを借地権と言い、建物を建てることができます。借りた土地の上に建物を所有する目的の借地権は、地上権と賃借権とに分別されます。
地上権と賃借権の違い
「地上権」がついた一般的な不動産はほとんどなく、不動産売買などで耳にする「借地権」と言えば、こちらの「賃借権」の方と認識しておくといいでしょう。
賃借権
賃借権の場合、地主さんの許可がないと建物を転売したり賃貸に出したりということはできません。建物に所有権はありますが、勝手に処分できないというのが地上権との違いです。
地上権
地上権がついている土地に建つ建物は、建物の所有者が売却することもできますし、賃貸として第三者に貸すということも可能です。その時に地主の許可は特に必要ありません。
また、地上権のある土地の上に建つ建物を第三者に転売した場合には、新しい建物の所有者がその土地の地上権を継続できることになります。
旧借地権

借地法は1992年に法改正が行われました。それ以前の借地権は「旧借地権」、1992年から施行の比較的新しい「普通借地権」「定期借地権」に分けられます。中古住宅として購入する住宅の土地に借地権がついている場合、旧借地権のこともあります。
旧借地権では存続期間を過ぎても地主側で正当な理由がないと返還を申し出ることができなません。つまり自動的に更新ができるような形になっていました。一方的に地主側の方で「更新しません」と言うのは認められていなかったのです。
ただ、旧借地権では地主側が「正当な理由だ!」という主張について借りる側が「正当な事由とは言えない」というお互いの見解の違いで多くのトラブルが起きていました。そこで法が見直されることになり、新たな借地権が施行されたのです。
1992年以降の普通借地権、定期借地権
1992年以前の旧借地権については、借地権の存続する期間は建物の種別によって異なってきました。しかし、新しい借地権である普通借地権では種別に関わらず「借地」の期間は30年と定められています。期間は定められてはいるものの特にお互いの理由がなければ、借地権が続きます。
新たに1992年から施行された定期借地権は「契約期間が定期で50年と定められており、期間が満了したら土地を返還しなければならない」という権利です。普通借地権と違い、時期がくれば建物を解体して地主に返還しなければなりません。
定期借地権は取り入れられてから50年経っていないため、これから様々な問題が起こる可能性があります。購入時には入念な調査と検討をおすすめします。
定期借家推進協議会ホームページ
http://www.teishaku.jp/index.html
借地権付きの建物の分類
現在、中古物件で借地権付きマイホームを購入する時には以下のいずれかであるかを確認する必要があります。
- 旧借地権(旧法):地主が主体で契約更新を辞めることが難しい
- 1992年以降の普通借地権:契約存続期間は30年。地主が30年で更新不可もできるが、異存なければ存続も可能
- 1992年以降の定期借地権:契約存続期間は50年。50年経てば強制的に地主へ土地を返還
旧借地権は法律そのものが「廃止」されて「新法」が施行されたのですが、1992年以前の借地権付き建物については旧法が適用されます。
例えば、1990年に取引した借地権のついた建物で、建物の種類により、20年とされていれば2010年までの存続期間となりますし、30年とされていれば2020年までの存続期間です。1995年の借地権付き建物は建物の種類に関わらず30年なので、2025年までの存続期間ということになります。
借地権のついたマイホームはお得?
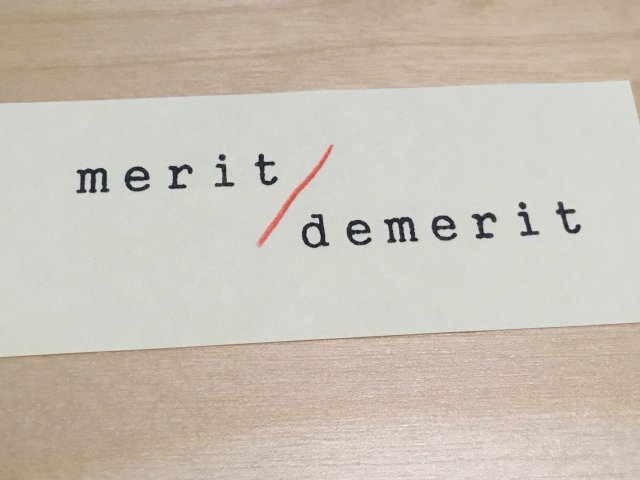
借地権付の建物の場合、土地を借りるということから「自分の資産にならない」と敬遠されがちです。何となく分かりづらいことが多いですが、メリットもあればデメリットもあるので両面から見てみましょう。
メリット
メリット
- 一般的な相場価格よりも安くマイホームの購入ができる
- 土地の固定資産税は納めなくてもいい
- 条件のいい立地があればお得
一般的な住まいの購入には、土地と建物の価格が含まれています。都市部と言われるような利便性の良い場所になると、人気もあるため土地の費用が高めに設定されています。
都会で便利で楽しい生活を送りたいとは思っても、立地が良い土地は土地の購入費用が高いので郊外を選ぶという方も多いでしょう。
借地権付きの建物を購入する場合のメリットはここにあります。「土地の所有権」ではなく「借地権」を購入するので、一般的には相場の50~70%の金額でマイホームを持つことができます。
【例:土地が4000万円、建物が1,500万円の物件】
| 土地を所有するケース | 4,000万円+1,500万円=5,500万円で購入 |
|---|---|
| 土地を借地するケース | 2,800万円(相場の70%だとして)+1,500万円=4,300万円で購入 |
このように購入時の金額は、所有権を持つ土地のケースと比べると安いのが魅力です。購入金額が多いため、住宅ローンの支払いも抑えられるメリットがあります。
相続時も安心
建物自体には所有権があるので、建物所有者が亡くなった場合は、建物の所有権だけでなく、借地権も相続人が存続することができます。
通常の借地権の場合、権利の期間が長く、正当な事由がないケースでは立ち退きを迫られることもありませんから、トラブルなどがなければ基本的には穏やかに自分の住居として暮らしていけるでしょう。
固定資産税
土地の所有者に課せられる固定資産税。条件がいい立地ならば税金も比例して高くなるのが当然ですが、借りている土地ですから固定資産税を納める必要はありません。
ただし、地代は毎月払う必要がありますので、納める地代によってはそれほどメリットに感じられないケースもあるかもしれません。
デメリット
デメリット
- 自分には資産にならない
- 地代は支払う必要がある
- 売却や建て替え時に自由にできないこともある
土地は資産にならない
大きなデメリットとしては借地権付きのマイホームの場合、土地を資産として残すことができません。建物に寿命が来て取り壊した後には、建て替えについて地主から承諾を得なければ自由に土地を使うことはできないでしょう。
また、住宅ローンを利用する時も地主の承諾が必須となります。
更新料
そして、購入時の金額は一般的な所有権の物件よりは抑えられますが、借地の期間の契約の更新時には「更新料」がかかります。
旧法、新法によって更新の期間や更新料については異なりますが、仮に更新間際の借地権付き中古物件を購入した場合には、更新料の負担もあります。(1992年導入の定期借地権については更新はありません)
国税庁 借地権の評価
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4611.htm
借地権付きの住宅の住宅ローン

借地権付きの中古住宅の多くは賃借権と言われています。「賃借権」の場合、地主の協力がないと自分勝手に売却することもできません。
土地を担保にできないのですから、万が一住宅ローンを対応した時には競売にかけることもできず建物を売却できす滞納分を返済することが難しい状態です。そういった背景もあり、金融機関の多くは融資を渋る傾向にあると言われています。
住宅ローンを組むためには
賃借権がついているから全く住宅ローンを利用できないということはありません。前述しましたが、建物の売却の時に地主の承諾を得さえすれば可能ですから、住宅ローンの際に地主に対して、「万が一、担保物件である建物が第三者に渡った場合には、賃借権を新たな建物所有者に引き継ぐ」などの承諾書を提出してもらうなどの手続きをすれば利用ができるケースもあります。
また、寺や個人の方が地主の場合、こういった状況に慣れていてスムーズに了承してくれることもあります。そのため金融機関側でも地主が法人の場合より、寺や個人の場合は借地権のついた土地の上にマイホームを購入するケースでも住宅ローンの利用をOKとしてくれることもあります。
いずれにしても、貸している側と借りている側の関係性もありますし、各金融機関の判断によるところが大きいので住宅ローンが無理とは一概に言えないでしょう。そもそも住宅ローンには担保物件だけでなく本人の収入なども総合的に加味された審査が行われます。地主から上手く承諾をもらえても、本人の収入や仕事面で思うように住宅ローンが通過しないこともあります。
住宅ローンに与える影響
借地権付のマイホームについては、自分に所有権がないという物件なので、住宅ローンの融資を受けるにも一般的な所有権の場合と違い、金額に制限が加わる、条件が厳しくなるなどの難しい面があります。
- 借入額が低くなる
- 連帯保証人が複数名必要
- 火災保険への加入が求められる
注意点
借地権の土地に建てられている実家が古くなり、子供夫婦が二世帯住宅への建て替えを希望するケースもあるでしょう。この場合、地主の承諾が得られると建て替えすることはもちろんできます。多くは、親の年齢や収入的な問題もあり、子供世帯が住宅ローンを組もうという計画になるのではないでしょか。
ここで注意したいのは、これから先に地主が変わってしまう可能性についてです。
第三者に対抗できるのは借地権者=建物所有者
建て替えする前の権利関係は、「借地権者=建物の所有者=親」です。この場合、地主が第三者(不動産業者)に土地を売却した場合、土地を利用する権利をそのまま主張することができます。地上権の場合は、基本的に地主に対して「登記をして欲しい」という請求権があるので借地権者については登記に記載されています。
一方、こういった登記請求権がないのが賃借権。賃借権の場合でも、借りた側の権利を守る効力があります。借地借家法では「登記がされていなくても、借りている土地上に建つ建物の所有者として記載されている人は第三者に対抗できる」と定められています。
つまり、土地を借りている人=建物の所有者であれば、借地権という登記がされていなくても、第三者に土地がわたった場合でも「土地を使用する権利」が主張できるという訳なのです。
借地権者と建物所有者が違う場合
また、借地権の名義でない子供が住宅ローンを借りるには、将来地主が変わってしまった時には「土地を使用する権利」で対抗ができません。ずっと地主が変わらなければ問題はないことなのですが、これから先のことですから「変わらない」とは言い切れません。
そこで、対抗できるようにするためには「子供側に借地権をうつす」という方法もありますが、贈与とみなされ贈与税を考えなければならないのです。
このように子供世帯が住宅ローンを借りるようなケースでは、借地権と建物の名義が異なるため考えるべき問題が多くなることを事前に認識しておくといいでしょう。
地主からの底地購入
「借地権」という権利が付着している土地のことは「底地」と言います。
地主側から見ると、底地は「地代」という収益によるメリットがあります。借り手側の地代の滞納がなければ、安定した収益がありデメリットはないかもしれません。ただ、むやみやたらに地代を値上げする訳にもいきません。
そこで、貸主と借主とお互いにメリットがあるのが、借主に底地を買ってもらうこと。借り手側にとっては、底地を購入することにより、その土地は所有権のある土地になります。今後、売却する時も「土地+建物」をセットとして売却することもできますし、資産としての価値が上がります。
底地
所有者が土地を貸すことにより収入(地代)のある土地(借地権や地上権付きの土地)のこと
底地を第三者が購入したら…?
地主が借地権をもっていない第三者に土地を売却する場合には、注意が必要です。考えられるのが底地を専門に買取する業者です。そういった専門業者は早期にその底地を現金化したがる傾向にあり、地主から土地を安く購入し、土地の借主に対し底地の購入を迫ってくるケースも考えられます。
対抗できる?
前項でお伝えしたように、建物の名義人が借地権者と同じであれば、こうした第三者にも対抗ができます。しかし、借地権者と建物の所有者が違うなど、権利関係において対抗できないケースの場合、買い取りをしなければならなくなることも考える必要があります。
「底地を購入して欲しい」と言われた場合には、一般的な土地の相場よりも安く購入できることになります。相場程度の高値で取引することのないように気をつけなければなりません。
底地を購入する時の費用のため、住宅ローンの申込みをする場合には、一般的担保としての土地評価は周辺相場よりも低く考えられます。
まとめ
借地権の付いている建物は、ひとくちで説明できない難しい部分が多くあります。一般的な不動産とは違い、条件やケースが複雑で分かりにくい点もあります。
購入時の権利関係の問題をクリアできればお得に感じられることもありますが、一方で住んでいる途中に相続などで問題が起こるケースも考えられます。相場よりも安く購入できるメリットはとても魅力的ではありますが、知識を持たずに購入を考えると後悔することもあります。
所有権との違いなどを確認するためには、専門的な知識にまで踏み込みつつ、検討していくことをおすすめします。

