住宅ローンの申込み条件を見ていると、「借換地」や「保留地」という言葉を見かけます。これは何かなと思った方も多いでしょう。
「借換地」や「保留地」は土地区画整理事業には深い関わりがあります。土地区画整理事業を主軸に、住宅ローンとの関係についても分かりやすくご紹介していきます。

目次
住みやすくするための事業「土地区画整理事業」
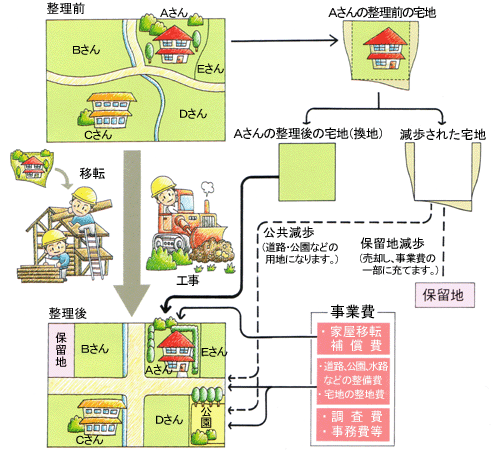
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000000006.html
日本中にある土地のひとつひとつは、道路があまり整備されていない時代からありました。自動車がそれほど普及していなかった時には、特に道路の幅は生活していく上で特に問題となるものではありませんでした。そのため、道幅が狭いことはよくあることでした。車がすれ違うのもやっとということもあるでしょう。
また、宅地の形状はバラバラで長方形や正方形など「整形」でないことが多く、それに沿った道路が造られたりすると、道路も規則性がなく曲線の道路が続いたり、曲がり角も雑で危険な箇所が今でも多く見受けられます。
このように古い時代からあるような住宅地エリアは、現代の生活には適していません。昔と比較すると自動車の保有台数も増えているので交通量も多くなっていまう。道幅の狭い箇所を頻繁に車が通るのは大変危険。危険箇所が多いと、人々の生活も脅かされますよね。
こういった住宅地は、日本中のあちこちに存在します。これらの土地の区画を整理し、安全なまちづくりをしていくことで、「住みやすい街」として活気づかせていこうというのが土地区画整理事業です。
土地計画事業の取組み
土地区画整理事業では、次のような取組みをして安全で住みやい街にしていきます。
- 道路を広げる
- 新しい道路を作る
- みんなの憩いの場である公園を新設する
- 宅地の形状を整える(不整形地から長方形や正方形の土地へ)
区画整理事業では、上記のように土地を整えていくために周辺の土地の持ち主から、少しずつ土地を提供してもらいます。これが「減歩(げんぶ)」です。そして土地区画整理事業の最中に提供者であった土地の持ち主が仮に住まう土地を「仮換地」と言います。
減歩をしても損をすることはない
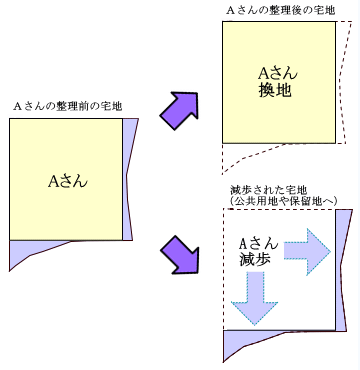
http://saitama-kukaku.jp/readjustment/system/
さきほどご説明したように、区画整理を行うにあたり周辺の土地の持ち主は少しずつ土地を提供します。つまり、所有面積は区画整理前のものよりも小さくなることが多いです。一見「損をしているのでは?」と思えますが、利用価値があがることにより「地価」もあがります。実は土地の価値を高めているので心配ありません。
一般的に不動産の価値は、利便性や周辺環境の良さによって算出されます。そのため、面積が同じ土地であっても、立地や接する道路状況などによってかなりの差が出るものです。
仮に減歩されたとしても、区画整理による「土地の形状が整う」「道路の幅が広がる」「周辺に公共の公園ができる」などで、住環境が良くなり資産価値が高まります。そのため、土地の提供をしたとしても損をすることはありません。
仮換地とは?
この事業によって、もともと所有していた土地である「従前の土地」は使用できなくなってしまいます。そのため、区画整理を行っている間に代わりの住宅地として使用できる土地を「仮換地」としてそれぞれに割り当てられます。
「仮」のものなので売買や建物の建設について気になるところですよね。売買自体は可能なので、不動産広告に「仮換地」という表示があったとしても購入することは可能です。
ただし、権利関係については土地区画整理事業がすべて終了するまでは「従前の土地」がベースとして考えられるので注意が必要です。
借り換え地の住宅ローン
仮換地物件を購入時(借り換え時も同じ)基本的に住宅ローンの申込み自体は可能です。
その時には、仮換地の登記はまだありませんので、すべて従前の土地に所有権や抵当権がつくことになるので注意しましょう。使える土地は「仮換地」ですが、抵当権が設定されるのは「従前の土地」です。
また、従前の土地と仮換地の面積が異なる場合には、後から清算金が発生することもあるので、不動産会社からしっかりとした説明を受けておくことが必要です。
換地処分とは?
仮換地として代用の土地を割り当てられても、従前の土地の所有権はそのまま変わりません。「従前の土地を使用することはできない」ものの、「所有権はある」という状態です。
従前の土地にそのまま居続けられると事業自体がスムーズに進みません。そのために、区画整理が進められている間に使用をしてもいい土地が「仮換地」として指定されます。
区画整理事業が終了すれば、換地処分が行われます。その際には、従前の土地から換地された土地に権利が移ります。
不均衡を調整する「清算金」
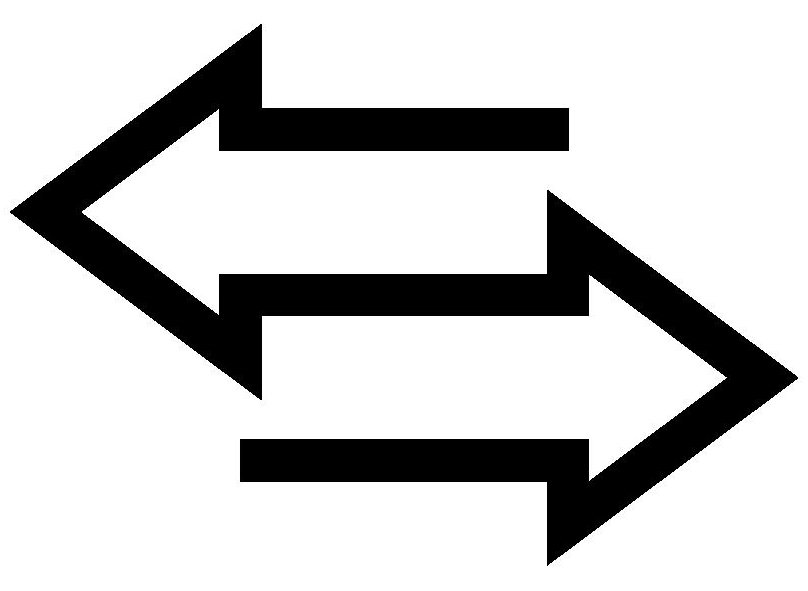
換地処分で気をつけたいポイントが従前の土地と仮換地の価値の不均衡です。一般的にはもともと所有していた土地よりも換地処分を受けた土地の方の面積が少ないことが多いでしょうが、なかには換地の側の面積が大きいこともあります。
区画整理する前に、形状の定まっていないような住宅地が多かった場合、面積の大きい土地もあれば小さい土地もあるでしょう。中には、周囲よりもかなり小さい土地もあるかもしれません。
その場合、小さい土地のままだと周囲との均衡が取りづらくなり、区画がいびつになってしまいます。全体的にバランスを保つためには、小さすぎる土地には面積を大きく、大きすぎる土地には面積を小さくした換地処分が行われることになります。
しかし、そのままではあまりにも不均衡となってしまいます。こうした不均衡を調整するのが清算金です。
【例】
Aさん:換地価格が500万円-従前の土地価格が600万円=マイナス100万円
Bさん;換地価格が500万円-従前の土地価格が450万円=プラス150万円
このような場合、Aさんには損(マイナス)があった分として100万円の交付がされます。また、逆にBさんには得(プラス)があった分として150万円の徴収の請求がされることになります。
仮換地の売買の際には、従前の土地の詳細についてもしっかりと確認しておくことが重要です。
保留地とは?
土地区画整理事業について知ろうとすると、「保留地」いう言葉に出会うこともあります。仮換地、保留地などとなかなか理解しづらいものです。
減歩によって土地を提供してもらい、道路を拡幅したり公園を作ったり公共的な利用の方法が取られます。また、その他に「事業を施行する上で費用に充てよう」と売却用に保留しておく土地があります。これを保留地と言います。
保留地と住宅ローン
保留地は言葉通り「保留されている」土地です。そのため、現段階では登記をすることができません。つまり、土地として使用できますが、区画整理事業が終わるまでは法的には宙に浮いた存在のもの。存在しないものとして扱われます。
登記がされていないので、「私の土地です」と所有権の主張ができません。そのため、多くの金融機関では保留地への住宅ローンの融資を受け付けてくれないのが現状です。
住宅ローンの利用には「担保」として、不動産に抵当権をつけることが必須なので、抵当権が設定できない保留地は難しいのです。
保留地でもOKな金融機関も
ただし、すべての住宅ローンがNGかというとそうでもありません。中には、登記簿謄本の代用として保留地証明書や保留地地図などをそえると申込みできる場合もあります。
金融機関のHPなどで「保留地」の住宅ローン申し込みについて記載があることも多いので、確認しておきましょう。
住宅ローンの利用が難しい仮換地のケースも
上記でご説明したように、基本的には仮換地であっても不動産の購入をすることもできますし、住宅を建設することもできます。区画整理が進められていて「仮」の状態の土地であっても、保留地と違って従前の土地の登記簿謄本が存在しますので、多くの場合は住宅ローンの利用が可能です。
ただし、難しい場合があります。それが従前の土地を他の誰かと共有していた場合です。
共有とは
不動産を複数の人が共同で持つことです。相続などで共有の名義として持つことも多くあります。その際、必ず持ち分割合があります。
例えば、Aさん・Bさん・Cさんの3人で所有していて、均等に持ち分があるとすれば、それぞれ1/3ずつとなります。共有のデメリットは、売却する時には共有者すべての同意が必要という点です。
また、共有者のうちの一人が亡くなっているケースもあるかもしれません。その際には、法定相続人となる人たちすべての同意が必要になります。配偶者や子供達など相続人が多くなってしまい、最終的には土地の共有者が増えてしまうことになります。初めは3人だった共有者が相続によって6人にも7人にもなることがあります。中には会ったことがない共有者が増えていくため、税金問題等でトラブルになる可能性も含んでいます。
住宅ローンの共有名義については次のページで詳しく説明しています。
共有名義って何?
共有仮換地での住宅ローンが難しい
土地区画整理事業というものは、短期間で行われるものではありません。長い期間を要するものですが、事業計画が完了するまでは従前の土地で所有権や抵当権の設定が行われます。そのため、従前の土地において共有名義となっている場合には、住宅ローンが難しいです。
例えば、3人で大きな一筆の土地を共有して利用していたケース。土地区画整理事業の計画上では換地処分後に3つに分けられるとします。仮に3つに分筆されても、それぞれが共有のままだとその土地の権利は共有者すべての人が持つことになります。
事業が終了するまでは従前の土地に対しての権利関係の設定ができるので、仮換地での住宅ローンを利用するために抵当権を設定し、その土地が換地処分後に3つに分けられても自動的に3つすべてに抵当権が移行されます。
それを避ける意味で、分筆された土地の所有権をすべて単独所有とすることが重要となってきます。しかし、土地区画整理事業が終了し、換地処分が行われた後まで待たなければなりません。こういった背景もあり、共有名義の仮換地の状態では住宅ローンの利用が一般的には難しいとされています。
まとめ
土地区画整理事業とはよく耳にしていても、その内容については難しい用語も含まれていてなかなか100%理解することはできないかもしれません。
また、内容によっては住宅ローンが組めなかったり、借り換えが難しかったりというケースもあります。「仮換地」や「従前の土地」の関係性を理解しておき、慎重に検討していきたい土地と言えます。

