「古家付き土地」は条件が良い立地にあると相場よりも安く購入することもでき、魅力的な物件と言えます。
しかし、一般的な更地と違って購入や住宅ローンで面倒なことも多くあります。「中古住宅と何が違いのだろう?」「古家付きでも住宅ローンが組めるの?」と不安や疑問を持ってしまいますよね。
今回は、古家付き物件の意味や特徴、購入時の注意点などについてのお話です。

古家つき土地と中古住宅の違い
不動産広告を見ていると「古家付き」という土地情報を見かけることもあります。古家とは中古住宅とはどういった違いがあるのでしょうか。
実は、明確に「これが古家」「これが中古住宅」という基準ありません。古家の一般的なイメージとしては、次のような感じではないでしょうか。
【古家のイメージ】
- 外壁が朽ちている
- 内部の床が抜け落ちる
- 周囲への草が生い茂っている
実際にはどのように売られているか見てみましょう。
中古住宅として売れない家

上記のような家の状態が悪い物件は「中古住宅」として売り出すことはできません。劣化がひどいまま売却しようとする不動産会社があれば、「こんな物件を売るの」と信用にも影響してしまいます。
そこで、築年数が経過し過ぎていて、「中古住宅」として売り出すのには抵抗があるような物件を「古家付き」と表示して広告に出すケースが多いのです。
築年数で決まらない

日本の住宅は、築年数が20年を超えてしまうと一般的には資産としての価値が「ゼロ」に等しくなるのが現状です。しかし、築年数だけで判断される訳ではありません。
築年数が30年、40年を超えても、定期的にメンテナンスをしていれば十分住み続けることはできます。途中でリフォームしたり、外壁塗装などを加えているとそこで新たな価値としても生まれます。その場合には、「中古住宅」として売り出されることになるでしょう。
古家付き土地に住む人も
両者の明確な違いはなく、その物件の状態を総合的に判断し、「中古住宅」「古家付き土地」と売り出されることが多いです。
実際には、現状でまだまだ居住できそうな「中古」を「古家付き」として売ることも多く、「古家付き土地」として土地を購入しようとした人が、建物を気にいってそのまま住むというパターンもあります。
売主はどちらでも構わない

古家付き土地はあくまでも「土地」としての売出ですが売主側は建物を解体せずに売却します。そのため、古家がついた状態の土地を購入した買主側が解体や整地に関わる費用を出す必要があります。
「建物価値がゼロだから土地の価格だけで売り出す」というスタイルですから、売主側では購入者が「解体する」でも「リフォームしてそのまま住む」でもどちらでも構いません。そのため線引きが曖昧になっているようです。
中には、「解体費用」を含めた意味で、相場よりも安く価格設定している古家付き土地もあります。立地条件がよければ、マイホームを建てるにはお得物件となるでしょう。
解体費用と住宅ローン控除
古家の解体費用は住宅ローン控除の対象になります。
古家付き土地は住宅ローンを組める?

一般的には、新築住宅や築浅住宅にしか住宅ローンが使えないのでは…?というイメージが強いかもしれません。しかし、中古住宅や古家付き土地など、築年数がかなり経過しているケースでも住宅ローンの利用は可能です。
借入期間が短くなる中古住宅
建築してから20年を過ぎるとほぼ価値がなくなる日本の住宅。住宅ローンを利用する時には、この「築年数」という部分により借入期間が異なっています。
通常、住宅ローンの返済期間は最長35年である場合がほとんどです。しかし、この返済期間は、築年数が古くなり資産価値が減少するとともに、住宅ローンの借入期間も減少していくのです。
借り入れる側の金融機関によってその借入期間の設定は異なりますが、多くの機関では「返済期間=50年-築年数」としていることが多いです。仮に築年数40年の中古住宅であれば、50年-40年=10年とかなり短い期間での返済が求められます。
借入希望の額にもよりますが、短い年数で返済するため月々の支払いが大きくなる傾向にあります。月々の支払い額が大きいということは、その分滞納のリスクも大きくなります。そのため、金融機関での住宅ローンは難しいこともあります。
基本的には、借入する本人の収入状況や担保となる物件の評価により、一概に難しいとは言えないのが現状です。
土地を先に購入する場合の「ローン」とは
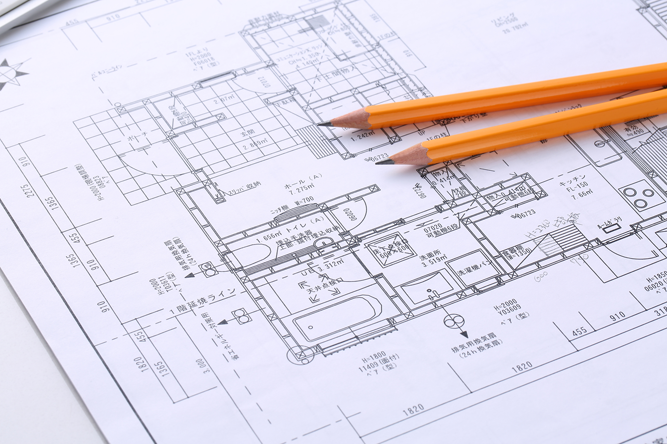
一般的には、住宅ローンを融資するためには「一括」で融資してもらいます。そもそも売買時に、「土地+建物」として購入するケースが主流でしょう。しかし、注文住宅でマイホームを建てる場合には、先に土地を購入します。
土地を先に購入時に必要な「建築計画」
住宅ローンは「マイホームを建設する」という条件のもと融資されます。そのため、先に土地を購入し、土地と建物のローンを分割して融資してもらう場合には、住宅ローンとは別に「先行融資」というローンを実行してもらう必要があります。
ただ、土地のローンを「先行融資」として金融機関へ審査してもらうには、マイホームの計画も考慮されます。先行融資としてローンを組む場合には、建築計画の具体性がないと融資をしてくれない金融機関もあります。
そのため、土地と建物を別に分けてマイホームを建築する「注文住宅」のケースでは、先にマイホームの建築計画の具体性が重要になります。土地だけ先に購入して、ゆっくり新築するなどでは融資に難色を示されることもあります。
古家付き土地の購入の注意点
古家付き土地の上の「建物」を解体して、更地にした後にマイホームを新築するという計画、「古家」という建物が付いている物件なので注意したい点がいくつかあります。
土地と建物の両方へ抵当権が設定
更地を購入するケースでは、ローンの担保としての抵当権は「土地だけ」に設定すればOKです。しかし、取壊し予定であっても建物が建っている「古家付き土地」は、土地と建物の両方の抵当権設定が必要になります。
抵当権設定の費用
抵当権を設定するには、ローンを利用する側で登記するために費用がかかります。
抵当権設定の費用
| 司法書士への手数料 | 司法書士が法務局で抵当権を設定してくれるので、その手数料として報酬です |
|---|---|
| 契約書の印紙代 | ローンを組む際には、金融機関との金銭消費貸借契約の契約書が必要です。借入金額によって印紙代は異なります。 |
| 登録免許税 | 法務局で抵当権設定を行う時に必要な費用です。借入額によって異なります。 |
解体予定なのに抵当権?
単純に考えると、取壊す予定の建物にわざわざ抵当権を設定するのは不要なのでは?と考えてしまいます。上記に記載したように、抵当権設定をするためには費用が結構かかります。できれば、その分を節約したいものです。
しかし、土地の上に建っている古家がある以上、土地だけに抵当権を設定するリスクは金融機関は回避したいのです。では、どんなリスクがあるのでしょうか。
競売による法定地上権の発生リスク
基本的に、土地と建物は一体となって利用されるものです。しかし、抵当権を土地だけにつけてしまった場合、担保が実行されて競売にかかってしまうことがあります。
競売で他人の手に土地が渡ったとしても、その地上に建つ建物は別人が所有しています。このケースでは、建物の所有者は強制的に土地を使う権利が生じます。それが「法定地上権」なのです。
通常、土地と建物が別の所有者となるためには「土地を使わせてもらう権利」である借地権を設定するなど、土地の所有者が不利にならないようにするものですが、競売では難しくなります。
つまり、古家といえども建物が取り壊されていない以上、土地と建物両方に抵当権を設定し、万が一の場合に土地と建物の所有者がバラバラにならないように金融機関ではリスク回避をします。
取壊し後には抹消登記が必要
抵当権のついている建物の解体には、抵当権者から同意を受けた後に解体作業をすることができます。古家付きの土地を購入後に、取り壊すことを事前に計画として金融機関に話しているケースでは、手続きも比較的スムーズでしょう。しかし、抵当権がついた古家を取壊しした後には、抹消登記が必要になってきます。
まとめ
このように、古家付き土地は「相場よりもお得」というメリットがあるものの、住宅ローンでは難しいことが多いです。また、先に土地を購入して先行融資を受ける場合には、取壊し予定の古家に対しても費用をかけて抵当権を設定する必要があります。
土地を購入後にゆっくりと新築計画をする…というのもいいかもしれませんが、住宅ローンを利用するなら早めに建築計画を作り、マイホーム完成に向けて進めていく方がいいでしょう。

