住宅ローンについて詳しい人でなくても「自営業を営んでいる人は住宅ローンが組みにくい」と聞いたことがあるのではないでしょうか。会社から給与として支払われている会社員とは違った部分が多く、住宅ローンを利用する際にチェックされるポイントも違います。
そこで、今回は個人事業主としてお仕事をされている方の住宅ローンの審査についてのチェックポイントを考えてみたいと思います。
個人事業主:住宅ローン審査のチェックポイント
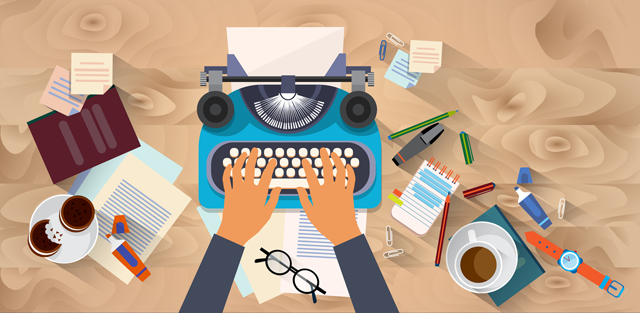
基本的に会社員や公務員などと比較して審査は厳しくなるものの、審査に通る可能性がゼロであるとは言い切れません。個人事業主や自営だからといって不利になる可能性はありますが、審査で見られる5つのポイントについてお話していきたいと思います。
個人事業主の住宅ローン審査:5つのポイント
- 収入
- 収入の安定性
- 業種と取引先
- 税金の滞納
- 頭金
ポイント1:収入
安定しない収入だからこそ、過去の事業内容については詳しくチェックされます。提出書類と収入について見てみましょう。
提出書類
まず、一般的な銀行からの借り入れでは確定申告書を過去3年分提出しなければなりません。つまり「個人事業主としてはまだ2年目」などは、住宅ローンの判断材料となる書類が3年分揃っていない状態ですから、多くの金融機関では申請が難しくなります。
メガバンクとフラット35の個人事業主対象の提出書類概要
| 金融機関 | 個人事業主が提出を求められる書類 |
|---|---|
| みずほ銀行 | 前年度納税証明書、過去2年分の確定申告書、過去2期分の決算報告書 |
| 三菱UFJ銀行 | 直近3期分の納税証明書(その1、その2)、直近3期分の確定申告書、個人事業者で許可を要する業種の場合は営業許可書も |
| 三井住友銀行 | 3期分の確定申告書、納税証明書等 |
| りそな銀行 | 3年分の確定申告書の写しと付表、3年分の事業税納税証明書、申告所得税納税証明書(その1・その2) |
| フラット35 | 過去2~3年分の確定申告書と納税証明書 |
見られる収入とは?

個人事業主が住宅ローン審査時にチェックされる収入とは「売上金額から経費を引いた額」になります。
- 住宅ローンでチェックされる収入 ⇒ 売上金額-経費
例えば、事業売上が600万円あったとしても、それが全て自分の収入となる訳ではありませんよね。自宅を仕事場としている場合には光熱費や通信費も経費として計上しなければなりませんし、仕事のために外出する場合は旅費も経費となります。また、宣伝広告費や消耗品費など経費として考えることができる科目は結構多いものです。
そのため、会社員として働いている方の「所得600万円」と個人事業主の方が「売上600万円」では内容的には異なります。
個人事業主の場合は、その額から経費が差し引かれた金額が審査の対象となります。確定申告の時には、青色申告決算書の損益計算書という書類を提出していると思いますが、その中の「差引金額」という部分が審査の時にチェックされます。
つまり、「経費が150万円かかった」というケースであれば、実際には差し引き後の金額の450万円の部分をベースにして借入金額が考えられることになります。すると借入ができる金額にも差が出てきます。
それぞれの金融機関では審査基準として所得の基準値を設けています。そのため、過去3年間の平均的な所得金額がそれを下回っているケースは住宅ローンの審査通過は難しくなると考えてもいいでしょう。
まとめ:個人事業主が住宅ローン審査時にみられる収入
- 2~3年の確定申告の書類提出が必要
- 住宅ローンの審査時に認めらる収入には経費は含まれない
ポイント2:収入の安定性

過去3年間の確定申告書を見た時に平均的に赤字のケースでは、まず住宅ローンの審査の通過は厳しいでしょう。そもそも、金融機関の中でも住宅ローンの申請に雇用形態を定めていないことも多いです。自営業でもOKという金融機関もあります。
しかし、審査時のポイントは「黒字収入があるか」ということなのです。そのため、黒字が2年続いていても1年赤字があれば審査は厳しくなってきます。また、黒字であっても平均値をチェックされますので、極端に低い年度があると可能性は低くなってしまいます。
審査が難しい場合
- 1年でも赤字がある
- 黒字であっても極端に売上が低い年がある
数年単位で計画的に
また、確定申告の書類では節税を目的に経費を多くあげているという個人事業主の方もいるかもしれません。売上に応じて税金を支払う率が高くなってしまうので、少しでも税金を少なくしたいという表れがあるのでしょう。ただし、これがマイホーム購入には裏目に働くケースも多いです。
住宅ローンを利用してマイホーム購入をしたいという個人事業主の人は、むやみに節税対策をすると審査に通過しない可能性を高めてしまいます。
「急に住宅ローンを組むことになったので、修正申告してしまおう」と考える方もいるかと思いますが、修正理由のチェックが入るので修正はしない方が無難です。もしかしたら住宅ローンにも通らず、追徴課税の憂き目に合うかもしれません。
個人事業主が住宅ローンを組む場合は数年単位で計画的に進める必要があります。
まとめ:個人事業主が住宅ローン審査時にみられる収入の安定性
- 3年間安定した売上が必要
- 3年間、計画的に確定申告する必要がある
ポイント3:業種と取引先
ひとくちに個人事業主といっても、その業務内容は異なります。返済は長い年数がかかるものなので、安定して稼ぐことができる業種か、流行に左右されにくい業種かなども見極められるポイントになります。
また、過去の取引先について確認されることもあります。大手の企業から継続的に仕事の受注を受けている場合、すでに事業としての基盤があると考えられることもあるようです。しかし、取引先があまり定まっていない、一度きりの取引先が多い場合には住宅ローン審査では不利になるケースもあります。
まとめ:個人事業主が住宅ローン審査時にみられる業種と取引先
- 安定した業種か確認される
- 取引先が定まっているかチェックされる
ポイント4:税金の滞納
個人事業主は、国民健康保険の加入と支払はすべて自分です。会社員の場合と違って毎月の給料から自動で引かれる訳ではありません。忘れることを防止するために、口座振替の申請をしている場合には納め忘れがなく安心ですが、納付書を銀行の窓口に持ち込み自分で支払っているケースでは、払い忘れということもあるでしょう。しかし、中には収入が少なく、意図的に滞納していることも…。
一般的に税金の滞納がある方は銀行側から難色を示されます。なぜなら、金融機関などの住宅ローンの滞納よりも税金の滞納の方が、回収の優先度があがるからです。そのため、万が一、事業の業績の悪化により各所への支払いが困難になったケースを考えると金融期間としては積極的に融資をしたがらない傾向があります。
まとめ:個人事業主が住宅ローン審査時にみられる税金の滞納
- 過去を含め、税金の滞納があると住宅ローンの審査通過は難しい
ポイント5:頭金

多くの場合、住宅を購入する時には思いつきで購入するなど「衝動買い」はしないものです。購入資金の足しにする頭金を貯めることが多いでしょう。
頭金は基本的に数百万円という大きなお金です。簡単に貯められるものではありません。頭金として初めに出せる金額があれば、金融機関に対しての「お金に対しての管理能力がある」と印象は良くなるという考え方もあります。
また、頭金があると住宅ローンの支払いも楽になってきます。そのため、購入資金の数十%を貯めてから住宅ローンの利用を考えるのが理想的です。
現在は頭金ゼロでも住宅ローンは組むことができます。しかし、住宅ローンの審査が厳しいと言われている個人事業主の方は、できるだけ頭金を多めに準備して審査に備えるといいでしょう。
まとめ:個人事業主が住宅ローン審査で注意したい頭金
- 頭金は多めに用意する
収入の不安定性を常に含んでいる個人事業主
安定している給料を得て、仕事を失うリスクが最も少ないのは公務員。そのため、住宅ローンでは公務員として働く方の審査は通過しやすいです。また、下記で詳しく述べますが会社員として働く方も雇用保険という制度に守られているので、転職の際にも安心と判断されます。しかし、個人事業主の方は雇用保険というカバー要素もなく収入の安定性に欠けると判断されてしまうのです。
収入は会社員より上…それでも
個人事業主として自営でお仕事をされている方の中には「会社勤めからフリーランスに転身した」という方も多いでしょう。「会社員時代よりも収入が多くなった」という方や才能を開花でき、企業との契約が増え軌道にのって、個人事業主として成功を続けている方もいます。自営で店舗を経営するなどで業績が好調であれば住宅ローンの利用も問題ないと考えるでしょう。
しかし、将来性については明言できません。現在高額の収入がある方でも、来年にその収入が確保できるかと言えば、それは誰にも予想できないことです。そういった背景もあり、会社勤めをしている方よりも住宅ローンが組みづらいと言われています。
フリーへ転身した個人事業主の落とし穴
- フリーランスに転身して収入が増えたとしても住宅ローンの審査は会社員より難易度が高い
個人事業主やフリーランス、給与所得者の違い
個人事業主と聞いてイメージできるのは、自営業者やフリーランスです。次に自営業やフリーランスについて詳しく見ていきましょう。その後に会社員との違いを説明します。
個人事業主、フリーランス、自営業者の違い
最近、「フリーランス」と言う言葉を耳にする機会が多くなったと思いませんか?カタカナ表示ですし、個人事業主や自営業など似たものもあり、分かりづらく感じている方もいるかもしれません。
なんとなく混同されがちなこれらの区分。まずはフリーランスから考えてみましょう。
フリーランス
最近では、会社に属さない働き方が注目されています。もちろん仕事をする上で多少の差異はありますが、プログラマーやカメラマン、イラストレーター、デザイナー、ライターなどフリーで活躍している方も多いです。一般企業から外注された単発の仕事を受注している方が多いでしょう。
これらの方々は、「物」を売って収入を得ている訳ではありませんよね。写真を撮影したり、デザインを考えたり、文章を考えたりなど、自分の技能を売るなどの仕事をして対価を得ていますが、その企業と「雇用関係の契約」を結んでいる訳ではありません。
フリーランスの例
- プログラマー
- カメラマン
- イラストレーター
- デザイナー
- ライター
仕事を受注して報酬をもらうという契約は「雇用契約」ではありませんから、依頼する仕事がなくなれば報酬を受け取ることはできませんし、企業側がフリーランスの人に対して保険に加入する義務もありません。このように個人が企業と直接仕事のやり取りをするのをフリーランスと呼びます。「働き方のひとつのスタイル」と考えてもいいでしょう。
個人事業主
そしてフリーランスのうち、開業届を出している方々は個人事業主という税務上の区分で言われます。また、フリーランスであっても「開業届は出していない」というケースもあります。一方、ネットショップを経営するなど「物」を販売しているケースはフリーランスとは言われてはいませんが、開業届を出しているなら「個人事業主」。
このように、個人事業主、フリーランス、自営業にはハッキリした違いが分からずモヤモヤすることもあるかもしれませんが、住宅ローンでは「収入が安定しない」と考えられるのは共通点と言えます。
給与所得者(会社員)と個人事業主(自営業者)の違い
働き方というものは人それぞれですが、住宅ローンでは一般的に「収入」「勤務先」などがキーポイントとなります。会社員にしても個人事業主にしても仕事で収入を得ているのは一緒ですが、付随する部分である保険関係や所得面などで大きな違いがあります。
保険関係で手厚く保護されている会社員

会社に雇われて「雇用関係」を結んでいる場合、毎月決まった給料を支払われている方がほとんどでしょう。中には「歩合制の給料」というケースもありますが、会社員として勤めている限り、多くの方は定収入が確保されており生活は安定しています。
そして会社員として働くことのメリットの一つには、保険関係がしっかりしていることがあります。
会社に勤める場合、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は違いますが、一定の収入がある場合には会社としては社員のために労働保険や健康保険、年金に加入しなければならないことになっています。雇用形態の中でも「正社員」は最も優遇されていて、これらの各種保険はすべて加入されています。
労働保険について

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」があります。
労災保険
労災保険は正式には「労働者災害補償保険」と言い、働いている中での負傷や疾病、死亡などに至った場合に、その内容に応じて保険金が支払われる制度です。もちろん、会社に行く途中という通勤途中も対象になります。労災保険は働く個人が負担することはなく、基本的には雇い主である会社が加入すべきものです。
雇用保険
一方、雇用保険ですが、離職した際の重要な収入となるものです。何らかの理由で会社を退いた場合、次の就職が見つかるまでは生活は非常に不安定になります。
そこで再就職先が見つかるまでの生活をサポートするのが雇用保険制度です。ちなみに加入条件や支給条件は異なりますが、契約社員やパートという正社員以外の方も雇用保険に加入することができます。
マイホームを購入するような方は、「今後もずっと働き続けたい」と思うのが当然ですよね。しかし、会社を辞めなければならないという不測の事態が起こることは可能性的にはゼロではありません。公務員として働いている場合であれば、職場が倒産することもなく、自分から職を辞さない限り生活は安定しているでしょう。
しかし、一般企業の場合にはそうはいきません。順調そうに見えても突然、「会社が倒産した」「リストラされた」などのケースはよくあることです。本人の年齢と雇用保険に加入していた期間によって違いがありますが、会社都合の退職による場合はすぐに失業給付金を受けることが可能。日々の生活のサポートとなり安心して再就職活動ができます。
健康保険について
住宅ローンを組む際に審査されるポイントとして、雇用形態の確認がありますが多くの場合保険証の提出を求められるでしょう。
健康保険は次のようにいくつかの種類があります。
- 国民健康保険
- 組合健保
- 協会けんぽ
- 共済保険
- 船員保険
基本的に上記にあげた「国民健康保険」は、正社員の方が加入することはありません。国民健康保険の被保険者は、自営業や学生、農業従事者、会社を退職した方などです。また、会社に勤めてはいても非正規雇用、パートなどの方は国民健康保険への加入となります。
共済保険は公務員の方が加入、船員保険は船員の方が加入と被保険者が決まっていますが、協会けんぽは契約社員等の「非正規雇用」の方も入ることができます。そのため、「協会けんぽの保険証を持っている=正社員である」と限らないケースもあるのです。
まとめ
近年、働き方は多様化しています。「会社」という組織に属さずに自分の能力を発揮し働くフリーランスという働き方も注目されている時代です。会社勤めと違って、収入アップも可能なお仕事なので「稼ぐ」チャンスも多いにあります。ただ、自分で経理作業をしたり、税金を納めたりなど大変なことも多くあります。
また、マイホーム購入の際に住宅ローンの利用では、審査に通過しにくいとも言われています。個人事業主として生計をたてている人は、住宅購入の際には慎重に数年単位で計画的に行うようにしましょう。

