親世代も子世代もお互い支え合える同居ですが、築年数が古い実家に住む場合、間取りや設備も古いため、親世帯と子供世帯という大家族で暮らすと不便に感じられる点が多々あります。
そのため、同居をきっかけにして全体的にリフォームをするという方も増えています。大きなリフォームをするとなるとローンの利用をするものです。ただし、親の名義の住宅に住む時には注意したいこともあります。
そこで、親との同居の際に考えなければならないポイント、家のリフォームなどに利用する住宅ローン問題について考えてみたいと思います。
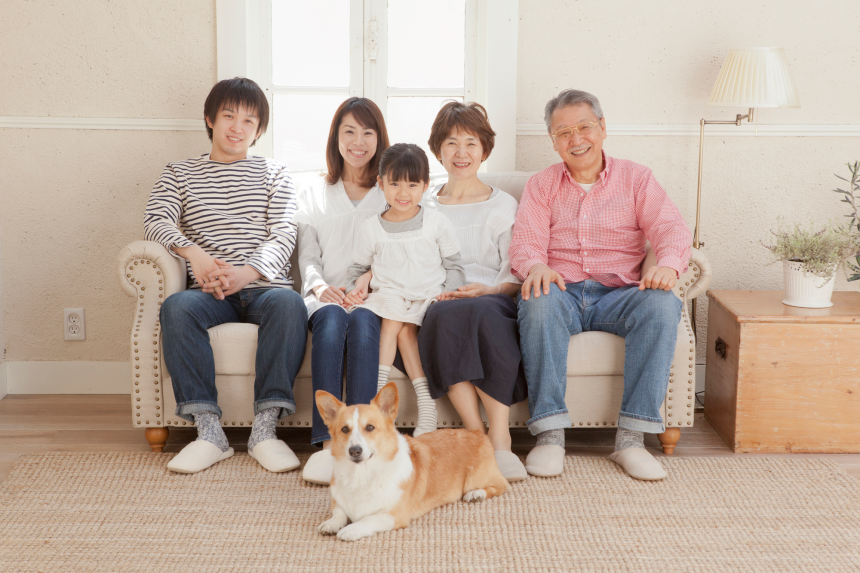
目次
親所有のマイホームに住む時に考えたいポイント

一般的な住宅の間取りは3LDK~4LDKというパターンが多いのかもしれません。皆が集まるリビング、夫婦の寝室が1部屋、子供部屋が2部屋という間取りならば家族4人でも十分に暮らせます。
そして、いずれ子供達が巣立っていくと親世帯だけ残り、子供が使っていた部屋は、荷物を置く部屋にする、子供達が泊まりに来た時だけ使う程度…なんてことはよくあることです。
そこで、子供達の方から「同居をしたい」と言ってもらえると空き部屋の有効活用にもなります。
実家に子供世帯が住むにはリフォームが必要
実家に使っていない子供部屋があれば、子供夫婦2人だけであれば、とりあえず住むことはできるでしょう。ただ、昔の間取りで使いにくい場合もあります。
また、子供が生まれて家族が増えれば、部屋が足りないという状況になることでしょう。それに、すでに子供が生まれている夫婦が実家に戻るには、部屋数が足りないため暮らしにくさが感じられることがあります。そこで暮らしやすいようにリフォームをしてから実家に戻るケースが多いです。
工事内容については、もともとの広さや間取りにもよるため一概には言えませんが、次のようなリフォームが考えられます。
- 部屋の壁紙を変える
- 畳の和室をフローリングの洋室にする
- 2階に部屋を増築する
- キッチンや浴室の設備を新しいものに交換する
- 間取りを変更する
- 二世帯住宅にする
壁紙や床材を変える程度なら、それほど高額な費用にはなりません。ただ、増築や設備の総入れ替え、間取り変更になると費用は高くなります。
二世帯住宅へのリフォームの場合は、最も高額になるケースです。2階にキッチンや浴室、トイレといった水回りを新たに増設するため、総費用は1,000万円以上かかってしまうことでしょう。その費用を貯金等の自己資金がなければ、金融機関から借り入れすることになります。
金額が大きいとリフォームローンが使えない!?

金融機関には、住宅購入の際に利用できる「住宅ローン」だけでなく、住宅改築の際の「リフォームローン」という商品もあります。ただ、前述のように大きなリフォーム工事の内容になるとリフォームローンの借り入れだけでは足りないこともあります。
また、リフォームローンと住宅ローンはそれぞれ特徴が異なりますので、一般的な特徴について見てみましょう。
リフォームローンと住宅ローンの主な違い
<リフォームローン>
| 担保 | 不要 |
|---|---|
| 返済期間 | 短い(0年程度) |
| 借入金額 | 500万円程度 |
| 審査基準 | 審査までの期間が短めで審査も通過しやすい |
| 金利 | 3~5%程度 |
<住宅ローン>
| 担保 | 必要あり |
|---|---|
| 返済期間 | 長い(最長35年程度) |
| 借入金額 | 500万円以上から借入可能 |
| 審査基準 | 審査までの期間が長い、厳しい基準もあり |
| 金利 | 2~3%程度 |
このように、リフォームローンと住宅ローンは特徴が違います。一般的にリフォームローンの場合は「担保」が必要ありません。そのため手続きがそれほど面倒でなく、住宅ローンと比較した時に審査が若干やわらぎ通過しやすいというメリットがあります。
「住宅を購入する時にしか使えない」と思いがちですが、実は住宅ローンはリフォームの際も使えます。リフォームローンは借入額が少ないので、小さな工事なら問題ありませんが、大きなリフォームをする場合には、借入金額の多い住宅ローンを考えるものです。
ただ、金融機関によってはリフォームローンであっても1,000万円を上限としていることもあります。
リフォームの費用を住宅ローンで借りる時の注意点

前項でお話したように、リフォームが高額になれば住宅ローンを借りればいいのでは…?と、安易に考えがちですが注意したい点があります。
親が住宅ローンを組めないことは多い
まずは、考えたいのは誰が住宅ローンを契約するのかということ。実家をリフォームして両親と一緒に住む場合、ほとんどが子供がリフォーム費用を借ります。なぜなら年齢的に親の方が住宅ローンを組めないためです。定年退職しているケースや健康面の問題でも難しいこともあります。そこで、まだまだ若く在職中の子供の方が住宅ローンの契約を考えることが大多数です。
住宅ローンの大前提は「本人名義」
住宅ローンが利用できる大前提は担保となる物件が「本人名義」かどうかということ。実家に戻るのであれば、自分も一緒に住むので、たとえ親名義の住宅であっても住宅ローンが借りられそうな気もしますが、実は難しいのです。また、自分名義でない住宅であれば住宅ローン控除の対象とはなりません。
住宅ローンの審査の前提となるのは、「担保となる物件の所有者であり居住者」でなければならないことを認識しておきましょう。
子供の名義にすればOK?!
親の名義のままだと住宅ローンの借り入れが難しいので、所有権を変更しなければならないことになります。「所有権の移転」を行うためには、その原因というものが必要です。
親が亡くなった場合には、「相続」という形で所有権の変更ができるわけですが、存命の場合には「贈与」という形になります。親子間の場合には、お金を発生させない「贈与」という形の名前だけの名義変更がほとんどではないでしょうか。
贈与という形で所有権を変更した場合、家の評価額にもよりますが実は贈与税の負担の心配をしなければならない可能性もあります。そのため、その負担を避けるため「子供がリフォーム費用を支払った」という工事代金で「親から所有権の一部を譲り受けた」という形にするという方もいます。そして、親と子供の共有名義にするケースもあります。
共有名義にする時に知っておきたいポイント
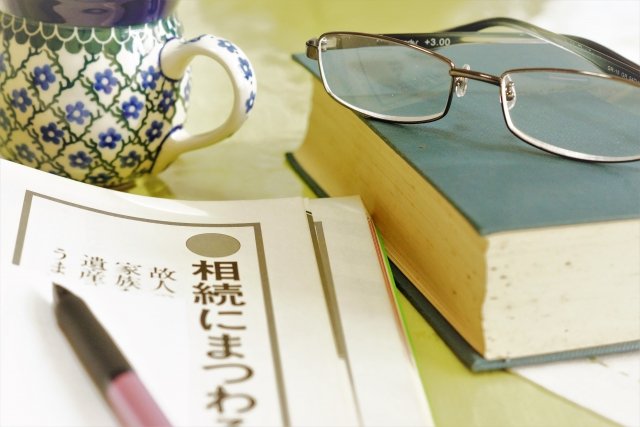
共有名義にして、子供達がリフォームの費用を負担するのであれば、親の経済的負担も減りますし、子供としては新築一戸建てやマンションを購入する際の高額な費用のことを思えばお互いにメリットが大きいものです。
避けられない相続
ただし、覚えておきたい点が「親の持ち分」のことです。お互いに元気なうちはあまり考えないものですが、いずれば「相続」という問題が起こってきます。共有名義にして「親の持ち分」がある以上、その部分は将来的に相続されなければなりません。
例えば、父親と長男の共有名義だった場合、父親の死後は母親や他の兄弟にも相続権が発生します。「一緒に住んでいるし共有名義なのだから最終的にはすべて自分のものになる」ということではありません。父親が生きている時には何のトラブルもない場合でも、亡くなった途端、他の兄弟が「相続権」を主張してくるケースも実は結構あります。
相続の際に揉める…というのは他人事ではありません。不動産にしても、貯金にしても「資産」がある以上、避けられないことです。そうやって「所有権」が引き継がれていくものです。
相続も含め家族で相談が重要
ただ、相続については子供側が考えるよりも「親」が考えるべきことでもあります。共有名義にするという結論に達した場合には、万が一の際の遺産の分配方法について考えてもらうことも必要です。
また、共有名義にするのは、住宅ローンを借り入れるためでもありますが、税金や手数料など費用がかかることも頭に入れ、じっくりと検討すべきことです。単に「住宅ローンを借りたいから」というだけで安易に考えずに、家族で十分に話し合うようにすることをおすすめします。
実家に住宅ローンがまだ残っている場合
そもそも実家も購入時には住宅ローンを利用しているということは多いですよね。すでに完済している場合には問題ありませんが、親の年代がまだ若いと「住宅ローンがまだ残っている」というケースもあるでしょう。
その場合、すでに実家に他の金融機関が設定した抵当権がついているということになります。これは「住宅ローンが払えなくなった」という万が一の場合の担保として抵当権が設定される訳です。そのため、先に他の金融機関の抵当権がついている物件は、多くの民間金融機関は難色を示します。仮に、その物件を売却しても2番目の金融機関には弁済できないケースも考えられるためです。
ただ、親がまだ在職中で返済状況に問題がない場合など、同じ金融機関に借り換えをする対策を行った方がいい場合もあります。
住宅ローンの共有名義については次のページで詳しく説明しています。
共有名義って何?
親名義の土地に新築する場合は?

「築年数が古い実家を壊して二世帯住宅を建てる」など、親が持っている土地に子供が一戸建てを建て替えするというケースも結構多いものです。
子供世帯にとっては「土地代」がかからずにマイホームが持てることになります。親は土地を提供し、子供は住宅ローンを組んで建物を提供する感じです。親の土地に建てるのだから特に問題なさそうな気もしますね。しかし、実際にはそうではありません。
賃貸料が必要?
それでは「土地の賃貸料を払えばいいのか?」と考える方もいるでしょうが、身内の場合にはお金を発生させないことがほとんどです。親が「使ってもいいよ」と言えば、無料で子供は使えることになります。親と子の間で取り決めることですから、契約書などは交わしませんが形式的にはこれを「使用貸借」といいます。
親子間での私用賃借についてはこちらのサイトで詳しく解説してあります。
大和ハウス工業株式会社 「使用貸借」と「賃貸借」とでは、課税はどう違うのか?
http://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souken/bcolumn/bclm05.html
親名義の土地は担保となる
通常、住宅を建設する時には「土地+建物」が担保となり抵当権が設定されます。これは、万が一、住宅ローンの返済ができなかった時に、その物件を売って返済に充てなければならないためです。「自分の所有は建物だけだから」と建物だけを売ることはできませんよね。つまり、土地と建物はセットで「担保」となるのが一般的なのです。
そのため、親の所有権のある土地に子供が新築する場合、親は「担保」として土地を提供しなければなりません。
「保証人」の種類がある
【保証人の種類】
- 連帯保証人
- 物上保証人
親名義の土地に二世帯住宅を建てるケースですが、親が「連帯保証人」となるか「物上保証人」となるかという点に注意しましょう。実は、この保証人の種類は金融機関によって異なります。
連帯保証人というのは、多くの方がご存知のように住宅ローンの契約者が返済不可能になった時に、連帯保証人が返済の義務を負う内容です。土地+建物を売却しても弁済できなければ、連帯保証人である親がその他の資産を返済に充てなければならないことになります。そのため、例え親であっても「連帯保証人」を嫌がるケースも多いでしょう。
一方、土地の名義人である親が物上保証人になる住宅ローンもあります。あまり聞き慣れない言葉ですが、これは「万が一の場合は、担保である土地を差し出す」という形になる訳です。連帯保証人と違う点が、子供が住宅ローンを払えなくなった時には、親は土地を失うだけで済むということです。
まとめ
親と同居をするということは、費用面などでメリットが多いのも事実です。何より親との距離が縮まり絆も深まります。
しかし、子供側がリフォーム代金を負担するならば、リフォームローンや住宅ローンとの関係についても知っておく必要があります。また、親との同居については、最終的には相続できるのかどうかなど、将来を見据えた判断が必要にもなります。

