住宅ローンは基本的に住宅ローンを申し込む本人の収入などや、担保となる物件により審査が通過するか判断されるものです。しかし、本人だけでなく家族関係がチェックされることもあります。
また、夫婦で住宅ローンを返していく場合には、配偶者が連帯保証人となることで審査の合否に関係することもあります。
そこで、家族関係がチェックされるケース、連帯保証人が必要なケース、不要なケースなどについてお話ししていきたいと思います。

目次
家族が住宅ローン審査に影響する?
住宅ローンを借りる時に、身内の借金が審査に影響してしまうのではないかと心配する方も多くいます。例えば、契約者の親や兄弟、妻が負債を抱えていたり、過去に自己破産をしていたりする場合などです。
基本的には、住宅ローンでは申し込みをした人の状況について詳しい審査が行われます。申し込む時点で、住民票を提出したり家族構成については聞かれますが、契約者の家族の信用情報などが審査対象となることはありません。
しかし、家族を連帯保証人とした場合には家族の信用情報もチェックされます。当然ですが、連帯保証人となる家族に大きな借金があると不利に働くことも多くあります。
まとめ:家族の信用情報
- 基本:契約者以外の信用情報は確認されない。
- 連帯保証人になる家族の信用情報は確認される。
慎重調査される場合
原則住宅ローンは「本人が居住する」ということが前提です。住宅ローンを利用する理由(融資した資金の使い道)に関しては聞き取りでチェックされます。そのため、住宅ローンを申し込む理由が曖昧なケースでは家族関係も慎重に確認されて、家族の問題が理由でNGとされることもあります。
例えば、夫婦二人で購入し家族で住むための住宅ローン利用は不自然な動機とは考えられません。しかし、「独身女性が一人で購入する」「若い女性が高齢の親と二人で一戸建てを購入する」などという場合には、不動産購入動機の背景を詳しくチェックされることもあります。
中には、配偶者の借金の問題で形式上離婚し、新たに独身という形で不動産を購入し後から同居するなどというケースも…。「何かを隠している」というような不自然さが疑われてしまいチェックされた結果、偽って申請したことが金融機関にばれてしまうとかなり心象が悪くなり、もちろん審査通過はできなくなってしまいます。

特に離婚が住宅ローンを利用する理由に含まれる場合は金銭トラブルが関係する可能性が高いので信用情報以外の書類などで確認調査されます。
基本的には申込者本人の現時点の返済能力が重要なチェックポイントなのですが、家族が負債を背負っていたなどが何かのきっかけで発覚してしまうと、将来的に返済能力が落ちてしまうと判断されてしまうこともあります。例えば、別居している親が負債を抱えていて、将来的に負債を相続してしまうと、住宅ローンの返済もできなくなってしまう可能性が増すことでしょう。
このように、家族の状況が審査に影響するかしないかは、ケースバイケースです。何よりも大事なのは、隠したりごまかしたりして住宅ローンを申し込まないことです。
まとめ:住宅ローンを組む理由で慎重調査される場合
- 理由の不自然さや、離婚が関与する場合は調査される。
- 調査で申請書の虚偽が判明すると住宅ローンに影響を与えることもある。
保証人が不要
「保証人」という言葉は多くの方があまりいいイメージを持っていないものです。そのため、住宅ローンを利用する時に「連帯保証人が必要」と聞くと、誰に頼めばいいかの不安が拭えません。
実は、利用する金融機関にもよりますが、住宅ローンでは必ずしも連帯保証人が必要な訳ではありません。
保証会社
多くの金融機関では保証会社を利用し「返済の保証」をしてもらう形をとっています。そのため「保証人探し」に奔走することもなく住宅ローンが組める形になっています。
保証会社が利用される理由

住宅ローンを借りている方(以降、債務者と表記)が返済を滞納してしまうと、債務者自身は「返済」と「生活費」とダブルで厳しい状況になります。同時に、返済をしてもらうことができない金融機関も大きなダメージを受けるものです。
そんな時に両者の負担を軽減させるシステムが保証会社です。債務者が返済できなくなった時に、残額を立て替えて、債務者の代わりに金融機関に返済してくれる役割をします。
ここで気をつけたいのは「借金がゼロになる訳ではない」という点です。保証会社から立て替えてもらった分は、保証会社へ返済を続けていく必要があります。
まとめ:保証会社と住宅ローン
- 保証会社は返済滞納時の金融機関のリスク回避のため利用される
- 保証会社を使うことにより、住宅ローン利用者は連帯保証人を依頼しなくて済む
- 滞納時に保証会社に立て替えてもらえるが、ローン自体は無くならなず保険会社へ返済する必要がある
保証料とは
保証会社というシステムは親戚や知人に対して頼みづらい「保証人」の問題をクリアしますが、保証会社を利用するには「保証料」がかかります。
「保証料」は借入の額や返済していく期間に応じて計算されます。金融機関や借り入れる金額などによって異なりますが、数十万円から中には百万円以上に及ぶこともあります。
保証料の支払は毎月の返済額にプラスできたり、初めに一括で支払ったりとパターンは様々です。
保証人がいなくて借りやすいと思える反面、保証料が高くなってしまうケースもあります。
まとめ:保証料とは
- 保証会社の利用は保証料がかかる
- 支払方法は毎月の返済額への上乗せ、一括払いなどがある
住宅ローンの保証料について下記のページでもっと詳しく解説してます。
住宅ローンの保証料とは
保証人も保証料も不要
中には、連帯保証人や保証会社への保証料が不要という商品もあります。このタイプを選べば高くなりがちな「保証料」の部分をカットして節約できます。
しかし、金融機関にとっては確実に回収したいため審査がかなり厳しくなることが一般的です。
連帯保証人が必要なケース
連帯保証人が必要なケースは以下の通りです。
収入合算

住宅ローンは長い期間返済するので、契約者の返済能力が重視されます。正社員などの勤務形態や勤続年数なども関係します。また、住宅ローンは「このくらい借りたい」という希望の借入金額があっても、本人の年収次第では希望の額を借り入れることができないケースも多くあります。
そこで申込者の収入にプラスして、配偶者の収入を合算して借入金額の基準にできることを収入合算といいます。
収入合算して住宅ローンを組む場合には、配偶者を連帯保証人や連帯債務者にして申し込むことが多いです。
収支合算については当サイトの下記ページで詳しく説明しています。
審査結果で判断

以下のような場合、審査結果で「保証人をつける」よう求めらることがあります。
条件的に厳しい
年収が少なかったり勤続年数が短いなど、収入が安定していないなど判断が難しいケース。
担保の名義人が異なる
担保の名義が住宅ローンの申込者以外の場合は連帯保証人が必要です。「親名義の土地に子供が家を建てる」が多いケース。
共有名義での購入
夫婦および親子が共同でお金を出し合ってマイホームを建てた場合、その不動産は持ち分割合のある共有名義の不動産となります。持ち分の割合はそれぞれの状況によって異なりますが、担保となる不動産を共有している場合、連帯保証人を求められます。
住宅ローンの共有名義については次のページで詳しく説明しています。
共有名義って何?
連帯保証人と連帯債務者の違い
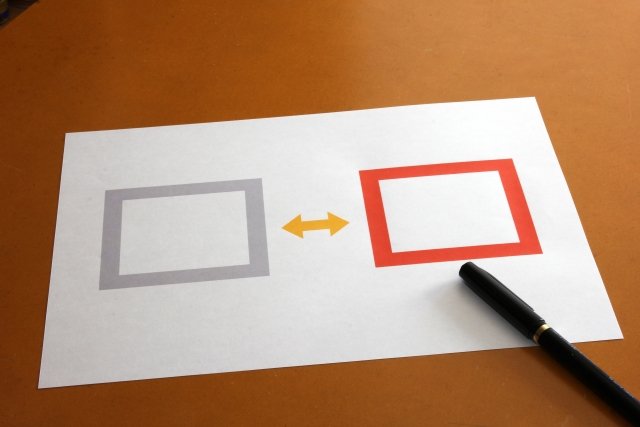
前項でお話した収入合算ですが、夫婦共働きのケースではよくある借り方です。一般的には収入の多い夫の年収だけで希望額を借りることができれば問題ないでしょうが、大きい金額を借りたいケースなどでは妻の収入も合算して計算されます。この場合、妻が連帯保証人になるタイプだけでなく、連帯債務者になることもあります。
言葉は似ているものの、内容的には異なる部分も多いのでしっかりと理解しておきたいところです。
「連帯保証人」の責任
例えば、夫と妻が収入合算で住宅ローンを組んだ時に、夫が債務者、妻が連帯保証人になったとします。この場合、住宅ローン返済をしている夫が基本的に返済する義務があり、住宅ローンの支払いをするのは「夫」です。
では、連帯保証人となった妻がどんな責任を負うかというと、夫が返済できなかった時です。そのため、夫の返済が滞ることがなければ、妻に対して「返済して欲しい」という責任を負わされることはありません。
「連帯債務者」の責任
連帯保証人は、「主」の債務者と同じような責任があると考えましょう。上記の「連帯保証人」のケースでは、債務者が支払えなくなった場合に金融機関から支払の請求を受けることになります。しかし「連帯債務者」の場合には、滞納に限らず返済請求をされる場合があり、その責任は債務者と同等です。
連帯保証と連帯債務の注意点
住宅ローン利用時に夫婦の収入を合算することがよくあります。その場合には、連帯保証や連帯債務で住宅ローンを組む可能性も大きいですが、事前にその違いや注意点をよく知っておく必要があります。
団体信用生命保険のリスク
団信は、正式には「団体信用生命保険」のことで、一般的には通称で「団信」と呼ばれます。住宅ローンのような長期的な借金には加入することが条件となっていることが多くあります。
団信の役割
多くのご家庭では収入の大きい夫が「大黒柱」として、生活費の多くを稼いでいるものです。ただし、住宅ローンの支払いは長い期間になります。途中で、住宅ローンを返済している人が死亡する、あるいは高度障害が残るなど、万が一のことがあった場合には団信が残りの住宅ローンの返済をしてくれるので、重要な役割を持つものです。
団信の対象
団体信用生命保険は、「主」として返済している本人だけにかけられます。そのため、夫婦で連帯債務や連帯保証などで収入を合算して返済しているケースでは、夫にのみ団信がかけられることになります。
夫の返済中に死亡では、団信がカバーしてくれるので妻の負担は安心ですが、妻が亡くなっ場合には基本的には何もありません。夫の負担が増えてしまうだけになります。
リスク回避の方法
そのリスク回避ためには、妻側が一般的な生命保険でカバーする方法もあります。これは借りる人の判断で行うものであり、仮に妻が亡くなって収入が減っても、夫の収入で返済できるのであれば必要はありません。
まとめ:団体信用保険と連帯保証と連帯債務の注意点
- 団信の保険対象は契約者のみで連帯債務者や連帯保証人は対象とならない。
- 連帯債務者や連帯保証人が別の保険でカバーする方法もある。
離婚時の連帯保証人
「連帯保証人」という形は簡単に外すことができません。連帯保証人を外すには「完済」「借り換え」「他の保証人を探す」と、どれも難しい方法となります。
特にトラブルになるケースが住宅ローンの支払い途中の夫婦の離婚時です。夫婦が離婚しても、連帯保証人はそのまま残ることになります。
例えば、離婚した後に住宅ローンの残っているマイホームに夫が残って住み続け、夫が支払いを続けていたとします。夫は返済途中で滞納してしまうと連帯保証人である妻に請求がきてトラブルとなります。
まとめ:離婚時の連帯保証人
- 離婚時も連帯保証人の効力は消えず、滞納時は連帯保証人へ請求される
ペアローンのメリット
団体信用生命保険がそれぞれ加入できる方法としてペアローンを組むこともできます。この方法は、各自でそれぞれ独自の住宅ローンを組む方法です。
例えば、4,500万円の借入をする場合、夫が3,000万円、妻が1,500万円の住宅ローンを契約する形です。この場合には、お互いのローンの「連帯保証人」となることが条件となります。ただ、一つの家庭で「住宅ローン」が二本立てとなり複雑な感じもするかもしれません。
ペアローンのメリットは、それぞれに団体信用生命保険に加入することです。配偶者に万が一のことがあっても、その分は団信がカバーしてくれます。残された一方の負担が増えることがなくなり、自分が契約した方の住宅ローンの返済だけを続けていくことになります。
まとめ
このように、住宅ローンは家族との関係が全くゼロではありません。また、夫婦で住宅ローンを組む場合には、連帯保証や連帯債務といった形態の違いがあると知っておくことも大切です。
憧れのマイホーム購入には、夢と希望が詰まっているものですが、背景にはこうした現実的な問題たくさん詰まっています。返済の途中で「知らなかった」ということがないよう、申し込む前にだいたいの内容を確認しておきたいものです。

